進行は宗教や事情により利用変更もありますが,基本は逝去から式事~送りへと葬祭では進行していきます。進行例 ご逝去→ 三ツ木屋へ連絡→喪主の決定→日時・場所の決定→死亡通知→ 枕経→納棺→祭壇飾り付け準備→供花や供物(盛籠)などの手配→通 夜→通夜振舞い→告別式→お別れ→出 棺→荼毘(火葬)→骨上げ→還骨法要(初七日)→精進落とし→ 焼香の順序 1例 父が死亡した場合 ①喪主・長男 ②母・妻あるいは本家 ➂喪主の妻、または故人の妻 ➃喪主の子供(故人の孫)または喪主の妻 ➄喪主の弟、または喪主の子供(故人の孫) ➅喪主の姉妹(他家の妻)、または喪主弟姉妹 ➆故人の兄弟姉妹、または喪主の妻の両親 ➇喪主の子以外の孫、または喪主の叔父叔母 ➈喪主の妻の両親、または喪主の叔父叔母 ➉喪主の義理兄弟姉妹、または喪主の子以外の孫 ⑪喪主の従兄弟姉妹 ⑫故人の友人、知人 日取り あらかじめ予定をしておくことが出来ない事柄ですので、遺族、近親者などで相談をし、各種手続きや関係者への連絡等一切の準備が済まされる時間を考えて、日取りを決定します。なお、友引の日は、休日としている火葬場がありますのでご注意してください。 通夜の進行 僧侶の入場で式は始まります。時には読経のあと短い説教をする場合もありますが、それが終わったら喪主以下通夜の参列者が順に焼香を済ませて式は終わります。式のあと別室で食事をふるまうのが普通です。   席次について 席順については、それ程こだわることはなく一応遺族は、祭壇に向かって右側に座り、喪主が棺の近くに座り故人と関係の濃い順に座っていきます。左側は、友人、知人等が座り、一般の会葬者は祭壇の正面に順に座っていただきます。  供花・供物の並べ方 普通、供花・供物は近親者、仕事の関係者、友人、知人というように関係の深い順に棺に近い所から並べます。香典の包みは、形よく多い時はいくつかに分けて積むようにします。生花や菓子折りなどは、祭壇脇の左右に並べます。 初七日の精進落とし 初七日の法要は、正しくは亡くなった日から数えて七日(関西では、その前日から)に営む法要ですが、招かれた方々の便宜さも考えて最近は、引き続き営まれる場合が多くなりました。精進落としは故人と親しかった方、手伝いをして下さった方々に残っていただき食事の接待をします。この場合、お残りいただく方にはあらかじめお伝えしておく事が大切で特にお手伝いをして下さった方には、必ず時間場所を事前に伝えましょう。いずれにしてもたてこんでいる場合ですから料理は仕出しにするとプライバシーも守られ便利です。  告別式 葬儀と告別式は、本来それぞれ別個の意義をもちます。近年では、同時に行うことが多く同じような意味に使われています。告別式の次第は、一般的には次の順序で行われます。営み方は、土地、宗派により異なりますので細部についてはご相談下さい。 ①一同着席 ②僧侶入場 ③開式の辞 ④読経 ⑤弔辞拝読 ⑥弔電代読 ⑦読経ー焼香 ⑧僧侶退場 ⑨閉式の辞 ⑩お別れ 焼香の順序は、特に社会的地位のある方が参列されている場合は、親族より先にお願いするのが礼儀です お別れ 告別式が終わり、霊柩車まで運ぶ前にまず祭壇から棺をおろし、棺の蓋をあけて式に供えられた花などを故人の周囲にうめながら対面してください。 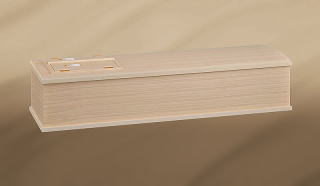 挨拶 会葬者が出棺を見送るために残っていますので、喪主または親族の代表が会葬者へのお礼をのべます。内容は故人の生前の厚誼に対するお礼と参列に対する感謝そのほか遺族としての今後の覚悟、変らぬ厚情の願いなどが多いようです。 遺骨迎え 遺骨を火葬場から直接墓地へ運んで、その日のうちに埋葬する例もまれにはありますが、多くの場合は自宅又はお寺あるいは、葬儀専用式場に戻って「あと飾りかお寺の内陣に安置されます。そのためには遺骨を迎える段のだれか(親族か葬家の事情い通じている知人など)が火葬場には行かないで式場に残り、近所の人に手伝ってもらうなどして片付けや準備をします。告別式終了後葬儀社が手際よく片付けて、後飾りを設けたりもします。小机ほどの大きさの二段程度で白布をかけ、燭台、線香立て、鈴などの仏具を置き葬儀の祭壇に飾った供物や生花を飾り、ここに火葬場から戻ってくる遺骨と遺影、白木の位牌を迎えます。遺骨は四十九日の忌明けまで自宅に安置し、法要をして墓地に埋葬するか、墓地の手配が間に合わない場合は寺院や霊園の納骨堂に預けて墓地の手はずか整ってから法要をして埋葬するのが一般的です。白木の位牌は忌明けまでの仮のものです。  詳しくはお問合せ下さい。 |